理由と根拠の違いについて
よく似た言葉に「理由」と「根拠」があります。
ビジネスシーンにおいても、プレゼンや討論の場で使われますし、小論文などの試験においても幅広く用いられる重要な言葉です。
しかし、これらの言葉の違いについては、きちんと教わる機会が少なく、混同されて使われることがとても多いです。物事をきちんと判断するためには、こうした言葉を正確に用いるということが欠かせません。
理由とは、物事のわけを表す場合に用いられます。「わけ」とは、ある出来事が起こったことで、別の出来事が関連して起こる筋道の中で、前の出来事を指す言葉です。
物事の原因ととらえられることもありますね。ですが、誰がどう見ても確かにそうだととらえられる(これを客観性といいます)事実としての原因とは異なり、理由にはそうした客観性は含まれていません。
しかし、理由を求められる場合、ある程度、他の人にも納得できる説明を求められることがほとんどです。そこで必要となるのが根拠です。
根拠とは、述べられる理由に対して客観性を持たせるための事実の集まり(データ)です。ただ単に理由を述べるだけでは人は納得してはくれません。
ですから、その理由となる事柄があってはじめて、ある出来事が起こったのだということを示す必要があります。そのために理由を支えるのが根拠なのです。
理由と根拠の実例
それでは、ビジネスシーンでよくみられる実例をみていきましょう。
全国で数十店舗を持つ会社で会議が行われます。議題は、ここ数ヶ月で落ち込んでいるA店の売上改善についてです。従業員の入れ替わりもあってか、予想していたほど売上が伸びません。
役員は従業員を募集する際、経験者など、より優秀なスタッフが集まるような採用条件を設けたり、従業員教育を徹底するよう担当者に指示します。
そこで、A店を含むエリアマネージャーが進言します。
「優秀な人材を募集することは確かに重要かもしれません。しかし、まずは店長を○○さんから□□さんに替えてみてはどうでしょう。」
「そう思う理由は何ですか。」
「○○さんは優秀ですが、従業員に対して高圧的な態度をとることがしばしばあります。そのため、A店の雰囲気は良いものとは言えません。職場の雰囲気は仕事の能率にも大きく影響します。売上が上がらない原因は、そうした職場環境にあるのではないかと考えられるからです。」
さて、エリアマネージャーは、A店の売上が上がらない原因が職場環境にあると考えています。そのため、職場の雰囲気を良くするために、店長を替えてみてはどうかと進言したわけですね。
しかし、それだけを伝えても、A店の売上が上がるだろうということを納得してはもらえません。その話が確かにそうだと思われるためには、根拠としてのデータを示す必要があります。
「そう考えられる根拠は何ですか。」
「こちらをご覧ください。各店舗の従業員からとったアンケート結果です。B店やC店、あるいはD店などでは、店長が替わって、職場の雰囲気が良くなったと答えている従業員の割合が8割にものぼります。そして、こうしたアンケート結果が得られた店舗では、従業員の入れ替わりがないにも関わらず、売上が上がっているのです。こうしたデータをみると、従業員よりも、全体の士気にかかわる店長を替える方が良いと判断しました。」
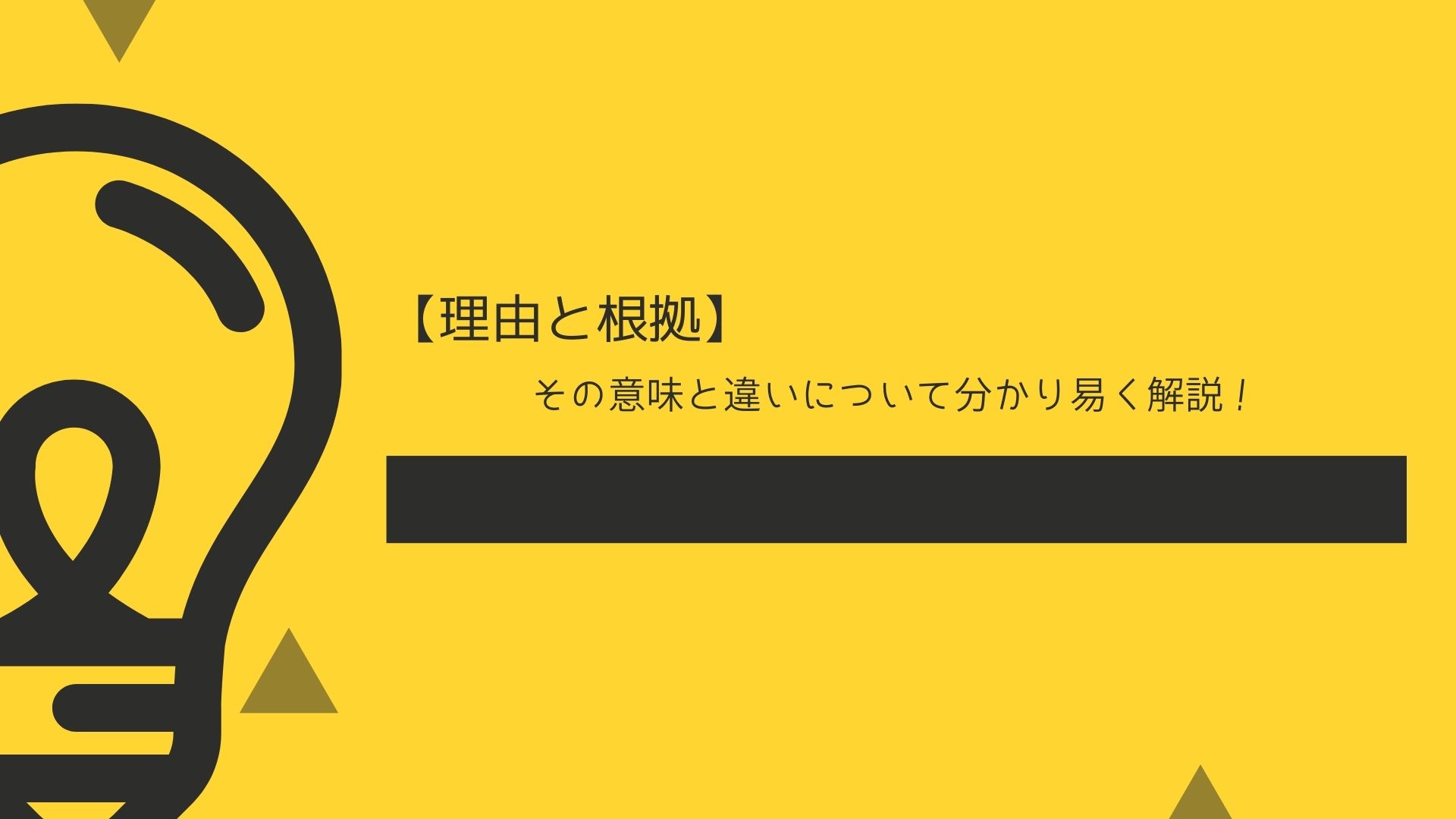


コメント