論理とは何か
考えるという行為に論理は付きものです。これがないと、考えるという行為が成り立たないくらい重要なものです。
ただ、論理という言葉を聞くと、とても難しそうとか、堅そうといったイメージを持たれる人が多いのではないでしょうか。でも、心配無用です。
実は、論理とは複雑な事柄を整理して、シンプルに捉えるためのものであり、物事を理解しやすくするためのものなのです。
論理という言葉を調べてみると、〈議論などの筋道〉などといった説明が見受けられますが、これでは抽象的過ぎます。意味がぼやけていてわかりづらいですね。
この筋道という言葉を、よりはっきりと表現すると因果律という言葉になります。因果の「因」は原因の「因」を、因果の「果」は結果の「果」を表します(ちなみに、「律」は決まり事を表します)。
つまり、因果律とは、物事には原因があって結果が生じるという決まり事を意味し、筋道とは、こうした物事のあり方を意味するのです。
例えば、コップに水を注ぎ続けると、いつか水は溢れ出しますよね。コップの許容量を超えたから、結果として、水が溢れ出したわけです。
また、坂道に丸いボールを転がすと、遮る物が何もなければ、ボールは転がり落ちていきますよね。地球の引力に引っ張られるから、結果として、ボールは下へと向かっていくわけです。
このように、あらゆる出来事は、原因があって結果が生じるという決まり事にしたがって起きていると、とらえられるのです。
論理的に考えるメリット
それでは、なぜ論理的に考えることが良しとされているのでしょう。もちろん、論理的に考えることにメリットがあるからです。そのメリットとは何か。それは〈パフォーマンスが上がる〉ということです。
論理とは、原因があって結果が生じるという決まり事にしたがった物事のとらえ方でしたね。言い換えれば、論理とは、そうした認識の構造ということができます。
複雑な物事を整理すると、その物事の仕組みへの理解が深まります。物事の仕組みがわかるということは、どこをどうすればより良い結果が出るのかがわかるということです。だから、パフォーマンスが上がるのです。
川向うにある農場から、生産物を市場に運んで売るという状況を想定してみましょう。ただ、農場から市場まで農作物を運ぼうとすると、はるか上流にある橋を通っていかなければならないとします。
いちいち、上流の橋を迂回していては、輸送のために使う車のガソリン代や時間など、いろんなコストがかかりますね。そこで、そうした物事の仕組みがわかっていれば、改善策をうつこともできます。
例えば、近くに新たな橋をかけることもできるでしょう。橋の建設費用など、はじめは費用がかかりますが、いちいち迂回する手間や時間などのコストを考えると、はるかに経済的になるかもしれませんね。
橋の建設費用に5000万円かかるとしても、輸送費用などに年間1000万円かかっていれば、5年も経てば新たな橋をかける費用はペイできることになります。
ですが、輸送にかかる諸々のコストや、作った物をどのようにして運んで売るのかといった仕組みを知らなければ、改善しようという発想さえ出てこないでしょう。物事の仕組みを知るということは、パフォーマンスを上げるためには欠かすことのできない条件なのです。
論理において重要なこと
客観的であること
論理というと、何か正しくて絶対的なものというイメージを持たれることが多いのですが、決してそんなことはありません。よくあるのが、因果関係と相関関係を混同してしまうことです。
ここでは詳しくは触れませんが、人間の認識に関わることなので、間違いを完全に取り除くことはできません。
それでも、論理について、きちんと理解しておくということは、誤った認識にとらわれないためにも、とても大切なことです。
論理においてなによりも重要なことは、客観的であることです。〈客観的である〉というのは、誰が見ても「確かにそうだなぁ」と思えることです。誰が見ても、確かにそうだと思われることには再現性があります。
たとえ、何度試してみても同じような結果になる、つまり、再現できるわけです。上記の例についても言えることですね。コップに水を注ぎ続ければ、必ず水は溢れ出します。
ボールの件もそうです。遮る物がなければ、ボールは坂道を転がり落ちていきます。何百回、何千回、何万回試してみても、同じような結果が得られるでしょう。このような場合、物事には〈再現性がある〉と言います。
同じ仕組みの物事に、同じ条件で取り組めば、「いつ・どこで・誰が」やっても同じ結果が得られる。こうした再現性があるから、パフォーマンスを上げるツールとして、論理は重宝されるのです。
それでは、ある物事について客観性があると、どのようにして判断されるのでしょう。それは、根拠が与えられるかどうかによります。
因果関係を正しくとらえるために
考えたり、人と話し合ったりする場合、論理的であることが求められます。論理的であるということは、考えや話が筋道だっているということです。つまり、物事にはある原因があって、結果が生じるというものの見方をするということですね。
しかし、ある出来事の原因が何なのかを特定することは、実は、それほど容易ではありません。ひょっとしたら、何の関係もない事柄を原因と思い込むことだってありうるのです。
例えば、今日では人体に有害だと知られている水銀が、昔は薬として用いられていたというのは、よく知られた話です。
古代中国の秦では、始皇帝が水銀を不老不死の薬として服用していたということですし、16世紀のヨーロッパでも、梅毒の治療薬として用いられていたということです。
不老不死や治癒という結果に対して、水銀が人体に及ぼす作用が原因としてとらえられていたわけですが、それが事実に反するということは、現在知られている通りです。
このような間違った因果関係で物事をとらえてしまわないために必要なのが根拠なのです。根拠とは、事実の積み重ね(データ)です。
限りなく同じ条件で物事をとらえた場合、ある事柄とある事柄の間に、きわめて密接なつながりを見いだせるとき、そこには因果関係があると、私たちは判断することになります。
水銀を服用している人間の寿命を調べたとき、ほとんどの人が短命であるというデータがたくさんあれば、「水銀は薬どころか人体にとって有害である」と判断されるでしょう。
短命という結果を、水銀の服用という原因で関連付けてとらえるわけです。逆に、半分くらいの人は平均寿命以上に長生きするというデータがあれば、水銀の服用を原因ととらえることはできないでしょう。そうした場合、他の原因があるのではないかと判断する方が適切だと判断されるのです。
このように、客観性を持つためには根拠が必要です。根拠があれば、因果関係があると、人は判断することになります。
極端な話をすると、誰が見てもバカバカしいと思われるようなことでも、根拠さえ与えられていれば、納得せざるをえないのです。つまり、物事を論理的に考えたり話し合ったりするためには、理由に対する根拠付けが、何よりも重要となるわけです。
まとめ
因果関係による認識の構造は、以下のようになります。
【原因】(理由+根拠)→【結果】
きちんと根拠付けられているから、誰がみても納得でき、再現性が得られます。
再現性があるから、「いつ・どこで・誰が」やっても同じ結果が得られるので、仕事において、効率の良い方法を考え出せれば、パフォーマンスは上げられることになるのです。
これは、別に仕事に限った話ではありません。ゲームやスポーツでも、成果を上げたい場合には、考える力というのは重要ですし、旅行の日程をスムーズにこなして、めいっぱい楽しみたいときなどにも効率な考え方は大切になります。
この効率的な考え方をするためには論理が不可欠なのですが、ひとりよがりの間違った因果関係でとらえることのないよう、きちんと根拠付けて、物事をとらえるように心がけましょう。
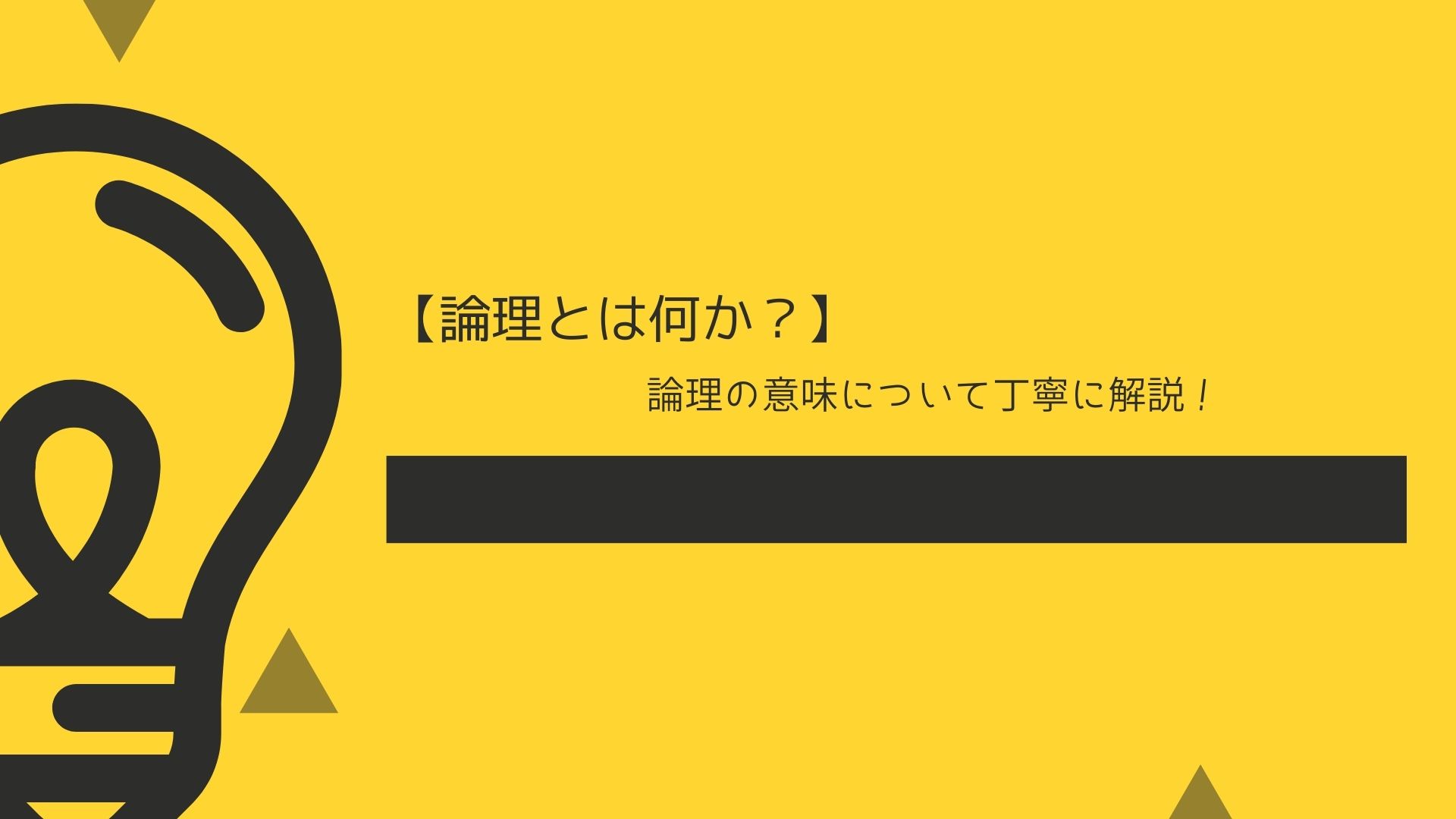


コメント